靴屋のマルティン
ある町にマルティン・アヴデーィチという、独り者の靴屋がいました。地下の一室が店で、そこで寝起きしていました。その部屋には明かり取りの窓が1つあるきりでしたが、そこから往来を行く人々の足元が見えました。靴を見ただけで、マルティンはそれが誰か分かりました。長いことその街に住んでいたので、たいていの人の靴は彼が直していたのでした。
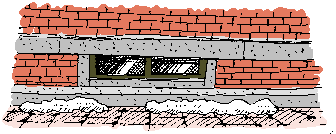 マルティンは職人気質の、腕の確かな靴屋でした。仕事がきれいで、品質もよく、納期をきちんと守りましたし、値段をふっかけたりしないので、仕事が途切れることはありませんでした。大もうけもしませんでしたが。
マルティンは職人気質の、腕の確かな靴屋でした。仕事がきれいで、品質もよく、納期をきちんと守りましたし、値段をふっかけたりしないので、仕事が途切れることはありませんでした。大もうけもしませんでしたが。
マルティンは奉公していた頃に結婚しましたが、何人かの子供を失い、妻も男の子一人を残して他界してしまいました。たった一人残った息子カピトーシカを、男手一つで育てましたが、ようやく仕事が手伝えるようになった頃、1週間寝込んだかと思ったら、あっさり先立ってしまったのでした。
せがれの埋葬が済み、マルティンは絶望の底に落とされました。あまりの不幸に神を呪い、死を願いました。息子の代わりに、なぜ老いぼれの自分を召してくれなかったかと、神様に何度も何度も苦情を言いたてました。いつしか教会にも行かなくなってしまいました。でも最近になって、人生の意味とか、救いについてぼちぼち考えるようになってきました。
そんなある日のこと、ペンテコステ(五旬祭)の間近な時でしたが、同郷の一人がマルティンを尋ねてきました。この人は8年間も諸国を巡礼して回っていたのでした。
久しぶりに二人で四方山話をしましたが、マルティンは自分の不幸と不条理の数々を愚痴ったのでした。
「あなたは信仰深いくていいですね。わたしには夢も希望もないし、願いといえば、早く死ぬことだけですよ。神さまにいつもそうお祈りしているのです。」
「マルティンさん、冗談は言わないでくださいよ。神さまのなさることにさからってはいけないんだよ。神さまはわたしたちの智恵より、ずっと深い考えを持っているのだから。その神さまのなさったことに、ケチをつけちゃいけないよ。息子があなたより先に亡くなったということも、きっと神さまがその方がいいと思われたからに違いないんだよ。」
「それなら、わたしは何のために生きなくてはならないのかな。」
「自分のためにではなく、神さまのために生きるのですよ。そうしたら、悲しまないで済むし、何でも堪忍できるようになりますよ。」
「・・・・・神さまのために生きるって、どうすればいいのですか。」
「キリストさまが言っておられます。あなたは字が読めるでしょう。聖書を買って読んでごらんよ。あなたの知りたい事は、何でも書いてあるからね。」
マルティンは早速その日のうちに大きな活字の新約聖書を買ってきて、読み始めました。
最初は「休みの日に読もう」と思っていたのですが、読み出すと毎日数ページ読まないと気が収まらなくなってしまいました。時にはランプの油が切れても聖書を置くのがいやになるほどでした。
読めば読むほど、神様が何を望んでいるのか、神様のために生きなければならないか分かるようになってきました。心に喜びが満ちあふれるようになりました。以前は床に入るときには亡きカピトーシカの事を思い出しては溜息をついていたのですが、最近では「グローリア(主に栄光あれ)、グローリア、主の御心のままに。」と言えるようになりました。
このことがきっかけになって、マルティンの生活ぶりはがらりと変わりました。以前は休みの日には居酒屋に行って紅茶を飲んだり、ウォッカを引っかけて陽気に騒ぎ、道行く人に軽口をたたいたり、絡んだりしていました。
しかし最近では朝早く起きて仕事に精を出し、仕事が終わるとランプを机に置き、聖書を取り出して読み始めるのでした。読めば読むほど理解も進み、心も晴れてくるのでした。
あるとき、いつもより遅くまで読んでいたら、次の文章に行き当たりました。
求める者には、だれにでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。
(ルカによる福音書6:30-31)
それに続いて、次のような文章がありました。
「わたしを『主よ、主よ』と呼びながら、なぜわたしの言うことを行わないのか。わたしのもとに来て、わたしの言葉を聞き、それを行う人が皆、どんな人に似ているかを示そう。それは、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので、揺り動かすことができなかった。しかし、聞いても行わない者は、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると、家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。」
(ルカによる福音書6:46-49)
マルティンは眼鏡をはずして聖書の上に置き、肘を机についてこのことを思いました。「はたして私の家は岩の上に建っているのだろうか、もしかして砂の上じゃないか。・・・・・ま、神 さまのお心から離れないように、とにかくまじめに一所懸命やろう。」
そこで寝床につこうとしましたが、聖書を手放すことができなくなって続く7章の百人隊長や寡婦の息子の話、金持ちのファリサイ人がイエスを家に招待し、罪ある女が主の足に香油を注ぎ、涙で洗ったこと、主がその女の罪を赦されたことなどを読みました。
そして、女の方を振り向いて、シモンに言われた。「この人を見ないか。わたしがあなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でぬぐってくれた。あなたはわたしに接吻の挨拶もしなかったが、この人はわたしが入って来てから、わたしの足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから、言っておく。この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。赦されることの少ない者は、愛することも少ない。」そして、イエスは女に、「あなたの罪は赦された」と言われた。
(ルカによる福音書7:44-48)
マルティンは考えました。「わたしもあのファリサイ人のように自分のことしか考えていなかったなぁ。自分がお茶を飲めて、暖まっていられればよかったし、お客さまの事など考えてもいませんでした。もしイエスさまがお客さまだったら・・・・」いつのまにかマルティンは寝入ってしまいました。
--------------------********--------------------
「マルティン!」
呼ぶ声にマルティンは飛び起きました。「どなたさまですか。」と答えて、部屋の中を見回しましたが誰もいません。また、トロトロとまどろみました。するとまた声がしました。はっきりした声でした。
「マルティン!マルティン!、あしたは通りに気を付けていなさい。私は必ず訪れます。」
マルティンはハッとなってイスから立ち上がりましたが、誰もいませんでした。「夢でも見たかな。」ランプを消し、寝床に入りました。
--------------------********--------------------
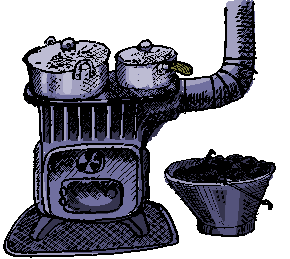 翌朝、マルティンは夜明け前に起き出しました。お祈りをして、暖炉に火を点け、肉とキャベツを切って鍋に入れ、暖炉に吊しました。お粥の鍋も吊しました。また、サモワールに水を入れ、火皿の木炭に火を 点けました。
翌朝、マルティンは夜明け前に起き出しました。お祈りをして、暖炉に火を点け、肉とキャベツを切って鍋に入れ、暖炉に吊しました。お粥の鍋も吊しました。また、サモワールに水を入れ、火皿の木炭に火を 点けました。
用意が済むと前掛けをつけ、窓際に座って仕事を始めました。仕事をしながら、夕べの「声」のことを思っていました。幻だったのか、夢だったのか。でも、本当に誰かが声をかけたような気もするのでした。「なあに、よくあることじゃないか」と自分に言い聞かせ、仕事に 精をだすことにしました。
とはいっても、窓から見覚えのない長靴が見えると、気になって、腰をかがめてそれを履いている人の顔を確認するのでした。新調のフェルトの靴は門番のでした。見慣れない粗末な靴は水汲み人夫のものでした。
底のすり減ったフェルト靴はニコライ帝時代の退役兵で、今は門番たちの手伝いをしています。柄の長いシャベルを持っていました。その爺さんの名はステパーヌィチといい、近所の商家にお情けで住まわせてもらっています。爺さんはマルティンが覗いている窓の前の雪かきを始めました。
マルティンは手元に視線を戻してつぶやきました。「何ということだ。ステパーヌィチ爺さんが来ただけなのに、救い主がおいでになったなどと思ってしまったりして。わたしもトロくなったな。歳をとったのかな。」
ところが10針も縫わないうちに、また窓の方に目が行ってしまいました。ステパーヌィチが壁にシャベルを立てかけ、暖かい窓に体をくっつけて一休みしていたのでした。おかげで部屋が暗くなってしまったのでした。「お爺さんもずいぶん高齢になったんだろうなぁ。見たところ、もう疲れて雪かきをする元気もないようだし。・・・・・お茶の一杯でも誘ってあげようか。ちょうどいい具合に、サモワールも沸いたみたいだからな。」
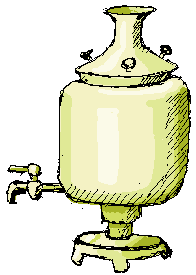 そこで急須にお茶っ葉を入れ、サモワールの煮え立つた湯をゴボゴボ注ぎました。そして窓ガラスのステパーヌィチの背をコツコツ叩くと、爺さんがのぞき込んだので、お茶を飲みにくるように合図し、扉を開けに行きました。
そこで急須にお茶っ葉を入れ、サモワールの煮え立つた湯をゴボゴボ注ぎました。そして窓ガラスのステパーヌィチの背をコツコツ叩くと、爺さんがのぞき込んだので、お茶を飲みにくるように合図し、扉を開けに行きました。
「まあ、お入りなさい。体、冷えたことだろう。しっかりと暖まっていきなさい。」
「やあ、それは有り難いです。骨まで冷えてしまって、ズキズキ凍りそうな寒さだったよ。」
お爺さんは戸口で足の雪を払おうとして、よろよろ倒れそうになりました。
「そんなに気を遣わないでいいさ。あとで拭くから。こっちに来てお座りなさい。」
マルティンはテーブルに2つのカップを置き、お茶を注ぎ、やっとイスに腰掛けた爺さんに1つ押しやりました。
「ともかく一服しなさいよ。」
爺さんは砂糖をたっぷり入れて、飲み始めました。マルティンは猫舌だったので、いつものように受け皿へ少しずつあけて、ふぅふぅ吹きながらすすりました。
「ありがとう。生き返ったみたいだ。」爺さんは受け皿にカップを逆さまにして置きました。「ごちそうさま」のサインです。でも、何となくお代わりが欲しい様子でした。
「もう一杯、飲みなさいな。」マルティンはお代わりを注ぎました。視線が窓の外にチラ、チラと動きます。
「誰かこられるのですか。」爺さんが尋ねました。
「うーん、誰を待っているかって、ちょっと恥ずかしくて言いにくいけれど。・・・・・ひょっとしたら、わたし、気が狂っているのかも知れないよ。・・・・・ぼけていたのか、寝ぼけていたのか分からないが、ある事を聞いたのです。・・・・・実はね、昨夜寝る前に聖書を読んでいたら、イエスさまの事をおもてなししなかったファリサイ人の話があったのです。・・・・・そのうち、ウトウトしかけたと思ったら、 "マルティン!マルティン!あしたは通りに気を付けていなさい。私は必ず訪れます。"って、2回も呼びかけられたんですよ。信じられないでしょう。ですから、その言葉が頭にこびりついて離れないのです。・・・・・それで、こうやって、ずっと待っていたのです。イエスさまをね。」
ステパーヌィチは頷きながら、話を聞いていました。2杯目を飲み終わると、再びカップを受け皿に伏せました。
「こんどは、あなたが元気で居られるように、祝杯しましょう。・・・・・イエスさまは、あちこち行かれたのですが、どこでも、誰にも相手にされなかった貧乏人や乞食にはとりわけ親切にしなさいました。お弟子にもエライ人はいなくて、漁師や職人ばかりだった。そう書いてありましたよ。」
「婚宴に招待されたら、上席に着いてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、『この方に席を譲ってください』と言うかもしれない。そのとき、あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、『さあ、もっと上席に進んでください』と言うだろう。そのときは、同席の人みんなの前で面目を施すことになる。だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」
(ルカによる福音書14:8-11)
マルティンはお茶を飲むことも忘れて、話すことに夢中になっていました。涙が頬をつたっていました。
「もう一杯、のみなさい。」マルティンは言いました。
「ありがとう、マルティン・アヴデーィチ。こんなに親切にしてもらって。おかげ様で身も心も温まりましたよ。」爺さんは十字架を切り、カップを押しやって立ち上がりました。
「とんでもない。また寄ってくださいよ。お客がいてくださると、嬉しいから。」
ステパーヌィチ爺さんは部屋を出ていきました。マルティンは急須に残ったお茶を飲み干し、また窓際に座って仕事を始めました。でも、頭の中はキリストのことで一杯でしたし、相変わらず窓の外の通行人に目が 移ってしまうのでした。
--------------------********--------------------
二人の兵士が通り過ぎました。一つは支給品の長靴。もう一つは自前の靴です。しばらくしてエナメルの靴を履いた紳士が通り過ぎ、パン篭を担いだパン屋が通り過ぎました。
女の足が見えました。この寒いのに木靴を履いています。窓の外を通り過ぎ、壁の前で足を止めました。マルティンが身を乗り出すようにして窓の外を眺めると、この町の者ではないようでした。赤ん坊を抱いていました。風を避けようと、壁に寄りかかり、赤ん坊を暖めようととしていましたが、くるむものも充分でない様子で、しかもみすぼらしい夏服を着ていました。
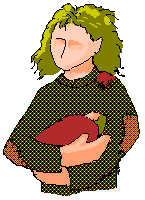 赤ん坊の泣く声がしました。お腹でもすいたのでしょう。なかなか泣きやみません。マルティンは立ち上がり、扉から出て階段の下から大声で呼びかけました。
赤ん坊の泣く声がしました。お腹でもすいたのでしょう。なかなか泣きやみません。マルティンは立ち上がり、扉から出て階段の下から大声で呼びかけました。
「おくさん!そこのおくさん!」
女は声に驚いて振り返りました。老眼鏡を鼻に引っかけた、職人風の、人の良さそうな爺さんがおいでおいでをしています。
「そこは、寒いでしょう。こちらの部屋にお入りなさい。赤ん坊の世話もしやすいでしょう。遠慮はしないで、おはいりなさい。」
女はマルティンに従って部屋の中に入りました。
「もっと、火の近くにお寄りなさい。唇が真っ青になっているじゃないか。暖まれば、おっぱいも出て来ますよ。」
「おっぱいはもう出ないのです。・・・・・今朝から何も食べていないのです。」
女は確認させるかのように、乳首を赤子の口に含ませようとしましたが、赤子はすぐにオッパイを吐き出して、再び泣き始めました。
マルティンは「なんてこったい」と頭を振り、暖炉の扉を開けました。お粥はまだ充分に煮えていませんでしたが、キャベツのスープはおいしそうに煮えていました。そこでスープを椀によそい、テーブルの上に置いて、パンを切ってスプーンと一緒にナプキンの上に用意しました。
「さあ、さあ。こちらに来てお食べなさい。暖かくなりますよ。・・・赤ん坊をよこしなさい。わたしにも子どもが居たので、あやすのは上手ですから。」
女は頷いて食卓に着き、十字を切ってから食べ出しました。マルティンは赤ん坊に頬ずりしたり、百面相をしたりしてあやしましたが、なかなか泣きやみません。そこで、指を赤ん坊の顔に近づけたり遠ざけたりしました。そうしたら、赤ん坊は興味を示し、泣きやんで手でつかもうとしてきゃっきゃっと笑い始めました。マルティンも嬉しくなって、赤ん坊と一緒に笑い出しました。
女は食べながら、ぼつぼつと身の上を話し出しました。
「わたしの亭主は兵隊で、8ヶ月ほど前に戦地にいったきりで、なしのつぶてなのです。仕送りも無いままに、子どもが産まれるまでは台所の下働きをしていたのですけど、やかましいって、3ヶ月前に仕事できなくなっちゃったんです。・・・・・しばらくは質屋がよいしていたのですけれど、売る物がなくなってしまって、乳母の口を探したのですが、痩せているから無理だって、断わられてしまったのです。それで、知りあいの人に頼んで、その人が働いている店で働くことになったのですけど、お店はとても離れているのです。来週から来てくれって言われたのだけれど、年の瀬も迫ってきて、この寒い中をどうやって通おうかと、途方に暮れていたのです。幸い、家主さんが親切な方で、家賃が溜まっていても知らん顔していてくださっているので、とっても助かっているのです。」
マルティンは溜息をつき、言いました。
「あなた、暖かい着物は持っていないのですか。」
「はい、きのう、最後のショールを20コペイカ(今の日本なら500円くらい?100コペイカ=1ルーブル)で質に入れてしまったものですから。」女はいつの間にかベッドで寝てしまった赤ん坊を抱き上げた。
マルティンも立ち上がり、壁の方でごそごそやっていたが、裏が毛皮の、古いけど暖かそうなマントを取り出して女に渡した。
「これ、持っていきなさい。上等ではないけれど、赤ん坊を包む足しにはなるから。」
女はマントを見て、マルティンの顔を見た。震える手でマントを受け取ると、わっと泣き出してしまいました。マルティンも思わず目頭が熱くなり、顔をそむけると、ベッドの脇机から手提げ金庫を取り出し、ごそごそかき回していましたが、何か握って、女の前に戻ってきました。すると女は言いました。
「おじさん、どうかイエスさまのご加護が豊かにありますように!。私を窓辺に導いてくださったのは、イエスさまでしょう。もしそうでなかったら、この子は今頃凍え死んでいたかもしれません。家を出るときにはそんなに寒くなかったのに、急に冷え込んできたのですから。私たちを窓から見つけて、哀れんでくださるように、イエスさまがあなたに親切心を吹き込んでくださったのでしょう。」
「ほんとうに、そのとおりだね。」マルティンは微笑んで応え、昨夜の出来事を話して聞かせました。
「不思議なことって、あるものですね。」女はそう言って立ち上がり、子どもをマントでくるみ、深く会釈し、部屋を出ていこうとしました。
「これ、持っていきなさい。」そう言って、マルティンは20コペイカ銀貨を女に握らせました。
「これでショールを買い戻すことができます。」女は十字を切りました。マルティンも十字を切り、外まで母子を見送っていきました。
--------------------********--------------------
マルティンはキャベツのスープを飲んで片づけ、また窓辺に戻って仕事を始めました。
針を運ばせながら、神経は相変わらず窓の外に向いていました。窓に人影が映ると、見上げて確かめました。顔なじみの人たち、見知らぬ人たち。でも、注意を引くような人はいませんでした。
しばらくして、物売りの婆さんが窓の外で足を止めました。リンゴの入った篭を持っていましたが、窓の庇の上に置いて、背中のズタ袋を地面に置きました。その袋には、どこぞの工事現場で拾ってきたのでしょう、廃材の木ぎれが一杯詰まっていました。婆 さんは担ぎやすいように、詰め直し始めました。
 小さな影がすり寄ってきたかと思うと、激しい罵声と泣き叫ぶ声が聞こえました。少年が婆さんのリンゴを1個くすねようとして、婆さんに掴まえられたのです。
小さな影がすり寄ってきたかと思うと、激しい罵声と泣き叫ぶ声が聞こえました。少年が婆さんのリンゴを1個くすねようとして、婆さんに掴まえられたのです。
マルティンが老眼鏡を落っことしてしまうほど慌てて外に出てみると、婆さんが少年の髪の毛をつかみ、げんこつでひどく叩きながら、「この泥棒め!警察に突き出してやる!」と叫んでいました。少年は「何も盗んでないよう!叩かないで!放して!」と、手足をばたつかせながら言っていました。
マルティンは少年の手を掴み、「婆さん、堪忍してあげてよ、堪忍してあげなよ!」と言いました。
「赦してやらないことはありませんよ。でもね、こっぴどく叱ってやって、性根をたたきなおすのが親切というものさ。とにかく、交番に引っ張っていかなくちゃ!」
「婆さん、いい加減に、堪忍してあげてよ。それだけぶたれたら、懲りているさ。ねえ、頼むから、赦してあげてよ。」
婆さんが手を放しました。少年は慌てて逃げようとしましたが、マルティンは少年の腕をつかんで言いました。「黙って行ったらいけないだろう。お婆さんにちゃんと謝まらなくてはいけないよ。リンゴを盗ったことを、わたしちゃんと見ていたんだから!」
それを聞いた少年は泣き出し、婆さんにわびて、許しを請いました。
「それでいいんだよ。さあ、このリンゴ1つ買ってあげるから。」と言って、篭からリンゴを一つ取り、少年に渡しました。「わたしが勘定払うからな、お婆さん。」
「こんな子どもを甘やかしたら、また悪いことをするに決まっているさ。何日もうなされるほど痛めつけてやればいいんだ。」
「お婆さん、そんなにムキになっちゃいけないよ。リンゴ1個でムチ撃たれなければならないんだったら、わたしたちの罪はどうやって償ったらいいんだろうよ。どんな罰を受けたらいいのか。」とマルティンは言い、聖書の話をしました。
そこで、天の国は次のようにたとえられる。ある王が、家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、一万タラントン借金している家来が、王の前に連れて来られた。しかし、返済できなかったので、主君はこの家来に、自分も妻も子も、また持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、『どうか待ってください。きっと全部お返しします』としきりに願った。その家来の主君は憐れに思って、彼を赦し、その借金を帳消しにしてやった。ところが、この家来は外に出て、自分に百デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、『借金を返せ』と言った。仲間はひれ伏して、『どうか待ってくれ。返すから』としきりに頼んだ。しかし、承知せず、その仲間を引っぱって行き、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは、事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで、主君はその家来を呼びつけて言った。『不届きな家来だ。お前が頼んだから、借金を全部帳消しにしてやったのだ。わたしがお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。』そして、主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと、家来を牢役人に引き渡した。あなたがたの一人一人が、心から兄弟を赦さないなら、わたしの天の父もあなたがたに同じようになさるであろう。」
(マタイによる福音書18:23-35)
「神さまは赦せと言っているじゃないか。・・・・・もし人を赦さなかったら、わたしたちも赦されないんだから。特にまだ分別が分からんヤツには。」
「あなたの言うとおりです。だけど、子どもは悪さするのもんですよ。」
「そうなんだよ。何が良いことか、年寄りのわたしたちが子たちに見せてあげなければ。」
「わたしも、そうは思うのだけれど。・・・・・ずいぶん年取ったけれど、わたしも働けるうちは働こうって、頑張っているんですよ。孫たちのためにね。その孫が、またかわいいんですよ。特にアクシュートゥカときたら、朝から晩まで"お婆ちゃん、お婆ちゃん"って、わたし無しじゃ日も暮れないのです。・・・・・そうだね、ほんのイタズラだったのですね。神さま、どうかこの坊やを守ってあげてください。」
婆さんが袋を担ごうとすると、少年は言いました。「お婆さん、僕が持ってあげるよ。同じ方角だから。」婆さんは頷いて、木っ端のぎっしり詰まったズタ袋を少年に渡しました。二人はなにやら楽しそうに話しながら、遠ざかっていきました。リンゴ代を請求するのも忘れていました。
二人の姿が見えなくなるまでマルティンは佇んでいました。部屋に戻ろうとしたら、階段のところに老眼鏡が落ちていました。幸い、傷はついていませんでした。腰掛けに座り、また仕事を始めました。
--------------------********--------------------
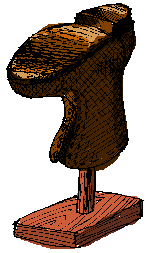 点灯夫が、街灯に明かりを入れて回っていました。仕事場も暗くなって、針に糸を通せなくなったので、ランプを灯しました。・・・・・長靴の片側が出来ました。要所要所をチェックしましたが、申し分のない出来でした。道具を片づけ、床に散らばった皮や糸の裁ちくずを箒で掃き集め、捨てました。
点灯夫が、街灯に明かりを入れて回っていました。仕事場も暗くなって、針に糸を通せなくなったので、ランプを灯しました。・・・・・長靴の片側が出来ました。要所要所をチェックしましたが、申し分のない出来でした。道具を片づけ、床に散らばった皮や糸の裁ちくずを箒で掃き集め、捨てました。
天井のランプをテーブルの上に移し、福音書を棚からとり出して机の上に置きました。
福音書を読み始めようとしたとき、昨夜のようなことが起こりました。後ろで何かの気配がします。振り返ってみたら、いくつか影が見えます。ぼんやりしていて、何の影かよく分かりません。
「マルティン、マルティン!、わたしがわかりますか。」
「どなたなのですか。」
「わたし、わたし。」・・・・・ステパーヌィチが姿をあらわしました。微笑んだかと思うと、消えてしまいました。
「今度はわたし。」・・・・・赤子とその母親が現れ、二人ともにっこりして、消えました。
続いて婆さんと少年が現れ、同じように笑いかけると、消えてしまいました。
マルティンは心が喜びで満たされました。十字を切り、福音書を読み始めました。
お前たちは、わたしが飢えていたときに食べさせ、のどが渇いていたときに飲ませ、旅をしていたときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれたからだ。』 すると、正しい人たちが王に答える。『主よ、いつわたしたちは、飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、のどが渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ、旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ、病気をなさったり、牢におられたりするのを見て、お訪ねしたでしょうか。』そこで、王は答える。『はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。』
(マタイによる福音書25:35-40)
マルティンは気づきました。主が確かにおいでになったことを。
